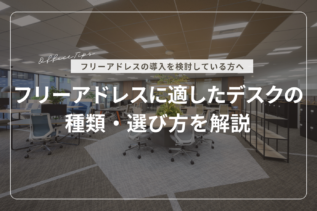自然災害の発生や社会状況の変化など、近年企業の事業継続を脅かすリスクが増えつつあります。そこで重要になるのが「BCP(事業継続計画)」の策定です。
本記事では、BCPの必要性や進め方、計画策定のポイントなどを詳しく解説。災害発生時にBCPに基づいて行動するプロセスについても掲載しています。初めてBCPについて検討するという方にも分かりやすくご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
BCP(事業継続計画)とは何を実現する計画?
BCPは正式名称を「Business Continuity Plan」といい、災害・事故・感染症といった緊急事態が起きたとき、企業における重要業務の継続、または事業の早期復旧のための計画を指します。あらかじめ具体的な方針や体制、手順などを示しておくことで、いざという時の道しるべにできます。
日本では2011年の東日本大震災をきっかけに、BCPの重要性が再認識されました。近年は、国内外で自然災害が頻発し、感染症のパンデミックも起こったことで、必要性はさらに増しています。
内閣府が令和6年に行った調査によると、すでにBCPを策定している割合は大企業で76.4%、中堅企業で45.5%という割合です。「策定中」「策定を予定している」の割合も含めると、大企業では96.1%、中堅企業で82.1%という高い結果となっています。
BCPは一部の大企業だけが必要なものという訳ではなく、中小企業であっても非常時に安全に事業を継続・復旧するためには欠かせないものです。
参照:令和5年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査|内閣府
BCPとBCMの関係と役割の違い
BCPと似た言葉に「BCM(Business Continuity Management)」があります。どちらも緊急時のために策定・活動しておくものですが、Plan(計画)とManagement(管理)には下記のような役割の違いがあります。
| BCP(Business Continuity Plan) | BCM (Business Continuity Management) |
|---|---|
| 緊急事態発生時に重要な業務や事業を中断させない、もしくは中断しても可能な限り早期で復旧させるための、方針・体制・手順を文書で示した行動計画 | BCPを継続的に運用・改善するために、平常時から行う管理活動全般 < 例 > ・予算・資源の確保 ・事前対策の実施 ・社内に浸透させるための教育や訓練の実施 ・計画の点検 ・継続的な改善と見直し |
BCP(Business Continuity Plan)
緊急事態発生時に重要な業務や事業を中断させない、もしくは中断しても可能な限り早期で復旧させるための、方針・体制・手順を文書で示した行動計画
BCM (Business Continuity Management)
予算・資源の確保、事前対策の実施、社内浸透のための教育や訓練の実施、計画の点検、継続的な改善活動など、BCPを運用・改善するため、平常時から行う管理活動全般。
< 例 >
・予算・資源の確保
・事前対策の実施
・社内に浸透させるための教育や訓練の実施
・計画の点検
・継続的な改善と見直し
いずれも非常時に事業を停止させないために必要なものですが、BCMはBCPが有効に機能・継続するために、教育や訓練、運用の見直しなどを行うことで計画のブラッシュアップを図るのが目的です。
BCPと防災計画の目的の違い
ではBCPと「防災計画」にはどのような違いがあるのでしょうか。防災計画は「防災マニュアル」ともいい、主に従業員の人命・身体の安全確保、施設など物的被害からの保護を目的としています。企業における具体的な防災計画の一例としては、以下の通りです。
- 食料や飲料水の備蓄
- 防災訓練の実施
- 安否確認のための連携
- 救護体制の確認
BCPは上記の防災計画にプラスして、事業活動の継続・早期復旧までを視野に入れて計画します。会社で定期的に行う避難訓練は「防災計画」、優先業務を特定した上でその事業を継続する方法を具体的に計画・文書化しておくのがBCPです。
BCPには防災計画も含まれていると理解しましょう。
BCPの必要性・メリット
ではなぜ企業にとってBCPは必要なのでしょうか。こちらでは具体的なメリットや効果とともに、詳しく解説していきます。
事業継続と早期復旧で売上損失・顧客離れを防ぐ
災害やパンデミックといった緊急事態に直面しても、BCPを策定しておくことで、事業の中断を回避したり、中断した場合でも迅速な復旧を図ることができます。これにより、売上の損失を最小限に抑え、顧客からの信頼を維持することにつながります。
特に緊急時は冷静で的確な経営判断が難しくなるため、あらかじめBCPによって最優先事業を明確にし、事業継続に必要な最低限の機能を確保しておくことが重要です。これは、事業中断による経営資源の損失を最小限に抑え、緊急時であっても事業をいち早く復旧・継続させるというBCPの基本的な考え方に基づいています。
安全第一!従業員を守る緊急時の対応
BCPの策定で最も大切なのは、従業員の安全と健康を守ることです。有事には人命の確保が最優先となり、それが結果として事業継続にも大きく関わってきます。
先ほど説明した通り、BCPには防災計画も含まれています。具体的な安否確認の方法や避難計画、感染症対策や物資の備蓄など、定期的な防災訓練や点検を通して、従業員の生命と身体を守るために必要な対策はしっかりと立てておきましょう。
迅速な対応が企業の信頼とブランドに与える影響
BCPの策定によって、非常時でも迅速な対応が可能になります。このようなときに的確で素早い対応ができる企業は、取引先や顧客から高く評価され、企業の信頼やブランドに大きな影響を与えます。
特に取引先との関係では、非常時の事業継続性は取引継続を左右する重要なポイントとなります。不測の事態においても迅速に対応し、事業を安定的に継続できる企業は、強固なビジネスパートナーとして取引先から選ばれやすくなります。
またCSR(企業の社会的責任)やブランド戦略の観点からも、BCPの策定は極めて重要です。災害時でも事業を継続することで、サプライチェーンにおける供給責任を果たし、顧客や取引先への影響を最小限に抑えることができます。さらに、復旧支援や情報提供を通じて、地域社会との連携や貢献を可能にします。こうした取り組みは、企業が社会の一員として責任を果たす姿勢を示すこととなり、ステークホルダーや消費者からの信頼を確固たるものにし、長期的な企業価値の向上に繋がります。
経営資源の棚卸と弱点把握による業務改善
BCP策定の過程で、人・モノ・カネ・情報といった経営資源の棚卸ができるというメリットがあります。その結果、企業の弱点や改善点を把握することが可能になります。
| 人 | 事業継続・再開を支える従業員の生命を守れる 取引先や協力会社との関係を洗い出せる |
| モノ |
在庫・不動産・設備機器・インフラの損失や破損を最小限に抑えられる 最小限の時間やコストで経営再開を目指せる |
| カネ | 緊急時の運転資金確保や支出の整理ができる 加入している保険の補償範囲の見直しができる |
| 情報 | 連絡先や契約関係、注文情報などを守る対策を立てることで、二次被害を防ぎスムーズな復旧が可能になる |
人
事業継続・再開を支える従業員の生命を守れる
取引先や協力会社との関係を洗い出せる
モノ
在庫・不動産・設備機器・インフラの損失や破損を最小限に抑えられる
最小限の時間やコストで経営再開を目指せる
カネ
緊急時の運転資金確保や支出の整理ができる
加入している保険の補償範囲の見直しができる
情報
連絡先や契約関係、注文情報などを守る対策を立てることで、二次被害を防ぎスムーズな復旧が可能になる
経営資源の棚卸をした上で企業としての弱点や改善点を把握できれば、平時の業務改善にもつながります。BCPの策定は非常時だけでなく、平常時にも大いに役立ちます。
BCPを構成する5つの基本要素
BCPを策定する場合には、次の5つの基本要素が柱となります。先ほど説明した、人・モノ・カネ・情報といった経営資源を棚卸する上でも重要なポイントになるので、具体的にどのようなことをすべきなのかを参考にしましょう。
人的リソースの適切な管理
BCPを策定する上で、人的リソースを適切に管理する必要があります。これは企業としての事業継続力を高めるためにも重要です。
災害が発生するのは勤務時間帯だけではありません。時間外に災害が発生したときに素早くすべての従業員と連絡を取り合うことはできますか?まずは従業員に安否確認の方法を周知させていきましょう。
同時に、非常時の役割分担表の作成やキー人材の特定も必要です。特に事業継続のためには、必要な業務を行える人材や重要な作業を任せられる人材の選定が不可欠。場合によっては、代替要員が必要になるケースもあるでしょう。そのようなときにでもスムーズに人的リソースを管理できれば、災害時でも事業を停止させることなく続けられます。
施設・設備の安全対策と災害への備え
施設や設備の安全対策、災害への備えも大切です。特に事業継続のためには主要拠点の安全確保や代替拠点・整備の準備、災害時の設備復旧手順の周知が欠かせません。
主要拠点の建物には、地震や台風、水害などがあっても耐えられる強度・安全性はあるでしょうか?代替拠点や設備が必要になった場合でも、あらかじめ準備・確保しておけば事業継続がスムーズにいきます。
そして忘れがちなのが、工場設備などの復旧方法の確認です。復旧方法を確認すると同時に自社の事業に優先順位を付け、その順番で設備を復旧させていきます。
場合によっては平常時、自動化されていたものを手動で行うなど、被害の状況に応じた臨機応変な対応が求められます。
緊急時に備える資金の確保と支出整理
BCP策定時には、緊急時の運転資金の確保方法や、優先すべき支出の整理が必要です。事業が通常に戻るまでの期間に応じて、資金の確保が必要となります。具体的には融資枠の確保や保険による補填、社内留保の利用などが挙げられます。
また緊急購入が必要な消耗品購入や、当面の操業のための支出枠も確保しておきましょう。こちらもあらかじめ優先順位をつけ、どの項目にどのくらい必要かを洗い出しておくとよいでしょう。
組織体制と責任者・連絡系統の明確化
BCPを事前に策定しておく際には、 非常時の意思決定体制や責任者の選定、連絡系統の明確化が欠かせません。
災害発生時など混乱した中でも、迅速かつ適切に意思決定できるように、あらかじめ役割を決めておきましょう。まずは統括責任者(リーダー)を決め、リーダーと連絡が取れない場合の代理責任者(サブリーダー)も決めておきます。
次に、部署や部門単位で誰が誰に連絡するのかといった緊急連絡体制を明らかにします。緊急連絡網などを作成し周知しておくことで、緊急時の混乱を避けられるだけでなく、スムーズな連絡が可能です。
クラウド活用と通信手段の多重化による情報保護
企業の大切な情報を守るためには、様々な工夫が必要です。企業には顧客データや業務データ、関係各所(従業員・役員・各拠点・協力会社)の連絡先など、事業を継続する上で欠かせない情報があります。
これらの情報を保護するためには、クラウドの活用や通信手段の多重化などの方法があります。クラウド活用のメリットは、比較的低コストで導入でき、場所を問わずに業務ができるということ。またバックアップの確実性が高く、セキュリティ対策がされているのも利点です。
災害時に通信が途絶えたときに効果的なのは、通信手段の多重化です。インターネットや携帯電話だけでなく、安否確認システムや無線電話、衛星電話など複数の通信方法を確保しておくことで、非常時の情報伝達がスムーズにいきます。
BCP策定の6つの進め方
ではBCPを策定するためには、どのような手順で進めたらいいのでしょうか。こちらではステップごとに具体的な策定のポイントをご紹介していきます。
1. 目的と基本方針を明確化する
まずはBCP策定の目的や、事業継続に向けた基本方針を明確にしましょう。場合によっては専門家の意見を参考にしながら、自社の実情に合ったBCPを策定していきましょう。
BCP策定の目的は、人命や資産の保護、事業継続です。どこまでの範囲(本社のみ・支店も含む・サプライチェーン全体など)にBCPを適用させるかや、復旧のための目標時間も設定していきます。
そして事業継続のためには、どのような対策(代替拠点の確保・材料仕入先の分散化・在庫の適正管理など)を講じればいいかを明らかにします。
特にBCPの策定には、上層部の積極参加や全社を挙げての協力が欠かせません。自社の経営理念や今後の事業戦略との整合性を取りながら、BCP策定の目的や基本方針を決めていきましょう。
2. リスク分析と影響度を把握する
次に想定されるリスクを洗い出し、売り上げ損失や顧客離れなどの影響度を把握する必要があります。まずは以下のようなリスクについて、自社の事業にどの程度影響が出るかを明らかにします。
- 地震
- 水害(洪水・大雨・土砂災害など)
- 風害(台風・竜巻・突風など)
- 火災
- 事件・事故
- 感染症の流行
- システム障害
- サイバー攻撃
影響度を数値化するときには「BIA(ビジネスインパクト分析)」が一つの指針となります。この分析結果によって、災害などでシステムや業務が停止した場合の影響度が明らかになります。
具体的には業務が停止した場合にどの程度の損失や支障が生じるかを数値化した「評価基準」と、最大許容停止時間・目標復旧時間といった「時間軸」を用いて分析していきます。この結果に基づいて、優先事項を決定し、リスク発生時に影響を評価することで、BCPの策定に活用できます。
3. リスクを優先順位付けする
リスクに優先順位を付けることも、BCPの策定には必要です。リスクの発生確率や被害の大きさに基づいて優先順位を付けられると、優先的に対策した方がよいリスクを洗い出せます。
具体的には「リスクマトリクス」を作成することで、よりスムーズに優先順位を付けられます。
リスクマトリクスとは、縦軸に被害規模や被害による影響度を、横軸に発生頻度(確率)を設定し、縦軸と横軸が交差する部分に起こり得るリスクを示した分析ツール。
図表によってリスクレベル(高・中・低)を視覚化することで、リスクの優先順位を判断するのに役立ちます。
リスクマトリクスの作成によって、企業が抱えるリスクの全体像を把握でき、より実効性の高いBCPの策定が可能になるでしょう。
4. 実行可能な対策を立案する
リスクの影響度と対応すべき優先順位がはっきりしたら、コストとのバランスを考えて、自社で実行可能な対策を立てていきます。
例えば、火災や自然災害などで事業の中断を最小限にしたり、早期の事業再開を可能にするには代替拠点の設置を検討しましょう。
そしてシステム障害時には、システムの多重化といった対策が必要です。これは自然災害だけでなく、サイバー攻撃やシステム機器の故障といったトラブルにも役立ちます。
さらにはシステムや事業を実際に動かす要員の訓練も欠かせません。いざという時の実行能力を高められるだけでなく、計画の不備や改善点も洗い出せるというメリットもあります。同時に従業員の防災意識の向上や、組織としての共通認識を醸成させるのにも役立ちます。
5. 計画書を作成し全社に共有する
BCPの内容が決まったら、規定や計画書など文書化して全社で共有します。文書を作成するときには、専門用語を減らし図表を多く用いるなど、誰が見ても分かりやすい内容で作成してください。
共有には、イントラネットや社内掲示板、紙媒体での配布など、複数の方法を組み合わせることが効果的です。また、メールやチャットでの周知、説明会の開催も有効でしょう。
すべての従業員がいつでも内容を確認でき、もれなく把握できるように、複数の共有手段を使い分けることが重要です。
特に社内向けのBCP教育にはある程度の時間がかかります。長期的に継続して全員が周知できる仕組みを作っていくのがポイントです。
6. 運用・見直しを繰り返して改善する
BCPをより実効性のあるものにしていくためには、定期的な訓練や見直しを通じて継続的に改善していくことが不可欠です。
年に1回以上の訓練では、災害を想定したシミュレーションを行います。また教育を通して、従業員の役割や責任を明確にしていきます。訓練後の反省会では、策定したBCPに改善点がないかなどを検討していきます。
他にも、後ほど詳しく説明するいくつかの環境変化やタイミングでの見直しも必要です。
BCPに基づく災害時の行動プロセス
では実際に災害が発生したときには、どのようなプロセスを経て事業を再開するのがベストなのでしょうか。こちらではBCPに基づいた行動プロセスを時系列でご紹介していきます。各プロセスでの判断基準や必要なもの、担当部署の役割についても参考にしてみてください。
災害発生時の被害把握と情報収集
災害が発生したら、まずは様々な方法で被害状況を把握します。
状況把握の方法は、現場から届いた写真や動画、報告書の他に、ニュース・自治体から得られる情報・インフラ状況などの外部情報を活用しましょう。その上で具体的な被害規模や影響の範囲を整理していきます。
とはいえ混乱した状況の中で、収集しなければならない情報は被害状況や災害情報の他、ライフライン情報や交通情報、拠点や設備の被害状況など多岐にわたります。
事前にこのような情報を正確かつ効率的に収集する仕組み(ツール)の準備をした上で、関係者間で密に連携が取れるような訓練をしておきましょう。
複数経路で迅速に行う緊急連絡と情報共有
次に社内外に対して、迅速に緊急連絡と情報共有を行います。
あらかじめ整備された連絡先リストと、複数の連絡手段(電話・メール・チャット・安否確認システム)を活用し、安否確認と必要な情報伝達を確実に行います。
災害発生時には、事前に作成した連絡網に基づき、電話による安否確認を迅速に行います。また、安否確認システムを使用する場合は、各従業員からの回答が100%となるまで徹底します。
同時に、負傷者の有無や状態を防災担当者に速やかに報告する体制を整え、状況に応じた初動対応に繋げます。
BCPを発動するタイミングと判断方法
定めておいた発動条件やタイミングによって、BCPを発動します。
発動の判断基準は、自然災害の発生状況や被害規模、事業停止時間や安全確保状況などを見て総合的に判断します。事前に明確にした判断基準を用いて、事業の優先順位や対応方針を迅速に決定します。
実際にBCPを発動させるかどうかの判断は、BCPの内容をよく理解した上層部や防災対策本部長などの統括責任者が行うのが一般的です。しかし上層部が現場に細かく指示を出すのが難しい場合もあります。そこで、BCPの実行フェーズでは、誰がどの現場の指揮を執るのか、そして誰が誰に指示を出すのかを事前に定めた指揮系統に基づいて、現場の対応を進めます。
優先復旧すべき業務とその判断方法
次に、どの業務を最優先に復旧するかの判断が必要です。事前に企業の存続にかかわる最も重要で、緊急性の高い「中核事業」を洗い出しておきましょう。具体的には顧客影響度や収益影響度、社会的要求といった側面から優先順位を付けていきます。
場合によっては、いくつかの事業を並行して復旧できるかどうかも判断すべきでしょう。
緊急時に中核事業に集中してリソースを投入できれば、スピーディーな復旧・復興が可能になります。
再開後のチェックと次回改善への取り組み
全事業復旧後は、振り返りによって次回に向けた改善点を抽出していきます。事業再開後のモニタリングや関係者へのヒアリングを通して、計画の問題点や改善点を明らかにし、次回計画に反映させることが重要です。
BCPは一度策定したらそれで終わりというものではありません。実際の発動や訓練などを通した見直しが必須となります。また新たなリスクの発生や技術の進歩、社内状況に応じた変更も欠かせません。内容を更新し続けることで、常に最新の状態にしておきましょう。
BCP策定のポイント・注意点
BCP策定や運用で失敗しないためには、次にご紹介するポイントや注意点に気を付けましょう。またありがちな失敗例やその回避策についても解説しますので、実際の運用時の参考にしてください。
教育と訓練でBCPを定着させる
BCPを社内で定着させるには、従業員への教育や訓練が必要です。具体的な訓練の方法は次の2種類があり、その内容や実施頻度、評価方法はこちらです。
| 訓練方法 | 机上訓練 | 実地訓練 |
|---|---|---|
| 内容 | 会議室などに従業員を集めて、各自の役割や計画の内容を確認した上で、非常時に計画通りに行動できるかシミュレーションする | 緊急事態が発生しBCPが発動されてから、対応が落ち着くまでの流れをすべて実際に行う訓練 |
| 実施方法 | ・計画の理解を深める「ワークショップ型」 ・与えられた状況に応じてどう行動すべきか考える「ロールプレイング型」 |
・企業内で独自に実施 ・自治体・消防などと合同実施 |
| 実施頻度 | 年2回以上 | 年1回以上(業種や事業規模によっては年2回以上) |
| 評価方法 | ・訓練後の自己評価をフィードバックする ・テストを実施してBCPへの理解度や緊急時対応の習熟度を把握する |
・「正確性」や「迅速性」など、いくつかの評価項目を設けて自己評価を行う(アンケートの実施も可) ・個人から出た結果をもとに、課題や改善点をまとめた報告書を作成する |
机上訓練
内容:会議室などに従業員を集めて、各自の役割や計画の内容を確認した上で、非常時に計画通りに行動できるかシミュレーションする
実施方法:・計画の理解を深める「ワークショップ型」
・与えられた状況に応じてどう行動すべきか考える「ロールプレイング型」
実施頻度:年2回以上
評価方法:訓練後の自己評価をフィードバックする テストを実施してBCPへの理解度や緊急時対応の習熟度を把握する
実地訓練
内容:緊急事態が発生しBCPが発動されてから、対応が落ち着くまでの流れをすべて実際に行う訓練
実施方法:・企業内で独自に実施
・自治体・消防などと合同実施
実施頻度:年1回以上(業種や事業規模によっては年2回以上)
評価方法:「正確性」や「迅速性」など、いくつかの評価項目を設けて自己評価を行う(アンケートの実施も可) 個人から出た結果をもとに、課題や改善点をまとめた報告書を作成する
介護福祉業界では年2回以上(在宅では年1回以上)行うことが義務化されていますが、一般企業の場合、いずれの訓練でも規定はありません。
しかし従業員の防災意識を高めるためにも、年に1回以上は実施することをおすすめします。
定期的な見直しと更新
中小企業庁では、実際のBCP発動後や年1回の訓練での見直しの他に、次のようなタイミングで計画を更新することを推奨しています。
- 大きな組織変更や人事異動があったとき
- 生産ラインの変更があったとき
- 製品・サービスの変更・追加があったとき
- 顧客状況・在庫状況に変更があったとき
実際にBCPの内容を変更・更新するときには、担当者が変わることも見越して更新履歴を残しておくことをおすすめします。
一例として、最初に策定した計画内容を第1版として、策定した日にちと「新規作成」という内容で記録します。次に内容を変更・更新したものを第2版として、日にちと理由(人事異動のため)や変更内容(防災組織の見直し)を記載します。
実効性を高める運用体制の構築
BCPをより実効性の高いものにするためには、運用体制の構築が重要です。具体的には、危機対応チームの編成などです。危機対応チームには上層部の参加を必須として、他に各部門・部署を横断した責任者を集めて編成します。
次に緊急事態発生時の事業継続や、復旧のための代替要員の確保も重要です。とくに災害時は、本人の被災や出社を阻む交通機関のマヒなどの問題が発生しがち。1つの役割に対して、メインとサブの2名以上体制で分担できるように体制を整えておきましょう。
BCPにおいて意思決定スピードを向上させるには、指示命令系統の確立と明確な役割分担がポイントです。事前の計画はもちろん、定期的な訓練やシステムの導入によって、緊急時でも迅速な情報共有や従業員間の連携が取れるように準備しておくことが大切です。
補助金・支援制度の利用でBCP導入を支援
国や自治体が行っている、補助金や支援制度を利用して、BCP策定に必要な設備や物品の購入ができます。
例えば、公益財団法人東京都中小企業振興公社の「BCP実践促進助成金事業」では、データバックアップ用のサーバーや基幹システムのクラウド化、安否確認システムの導入などに対して、申請下限額を10万円、上限額を1,500万円(ただし基幹システムクラウド化の助成上限450万円を含む)とした助成を実施しています。こちらの申請受付期間は、最長で2026年1月14日までとなっています。
場所にもよりますが、都道府県以外でも市(区)独自で実施している場合もあるため、会社所在地がある自治体に、こういった制度がないかチェックしてみましょう。
ICTツールやシステムとの併用
緊急時の情報共有やデータ管理には、システムやICTツールの活用も有効です。具体的なツールとその特徴・メリットを以下にまとめました。
| ツール | 安否確認アプリ | クラウド共有サービス | データバックアップ システム |
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・Webブラウザのようにログインの必要がない ・プッシュ通知機能があるので、見落とすリスクを回避できる ・家族の安否確認や外部システムとの連携、気象庁が発表する情報の自動配信機能などがある |
クラウドにデータがバックアップされるので、万が一社内サーバーが破損してもデータを安全に利用できる | サイバー攻撃や災害で社内にあるデータが消失しても、クラウドやデータセンターに保管することで、いつでもデータを復元できる |
| メリット | スマートフォンや携帯電話、メールや固定電話など複数の手段に対応していると、いずれかの通信手段が使えなくても安否確認が可能 | 社内外の人と安全にファイルを共有したり、場所を選ばすにデータへのアクセスが可能 |
・定期的な自動バックアップが可能で、運用の負荷を軽減できる ・迅速にデータを復元できるので、事業停止の期間を大幅に短縮できる |
安否確認アプリ
特徴:・Webブラウザのようにログインの必要がない
・プッシュ通知機能があるので、見落とすリスクを回避できる
・家族の安否確認や外部システムとの連携、気象庁が発表する情報の自動配信機能などがある
メリット:スマートフォンや携帯電話、メールや固定電話など複数の手段に対応していると、いずれかの通信手段が使えなくても安否確認が可能
クラウド共有サービス
特徴: クラウドにデータがバックアップされるので、万が一社内サーバーが破損してもデータを安全に利用できる
メリット:社内外の人と安全にファイルを共有したり、場所を選ばすにデータへのアクセスが可能
データバックアップシステム
特徴:サイバー攻撃や災害で社内にあるデータが消失しても、クラウドやデータセンターに保管することで、いつでもデータを復元できる
メリット:・定期的な自動バックアップが可能で、運用の負荷を軽減できる
・迅速にデータを復元できるので、事業停止の期間を大幅に短縮できる
自社独自のシステム構築や管理が難しいときには、月額利用が可能なプランやシステムの導入がおすすめです。いざというときに迅速に安否確認をしたり、業務を再開できるよう、必要に応じてこのようなサービスやシステムの導入を検討しましょう。
実際にBCP対策をしよう
BCP対策は「分かっているけれど、どこから始めればいいのか分からない」という声が多く聞かれます。ここでは、企業が取り組むべき4つのポイントをご紹介します。
これらはいずれも、リリカラでのご支援が可能ですので、実際の取り組みを進める際にぜひ参考にしてください。
従業員への防災啓もう研修
防災の基本は「自分の身は自分で守ること」です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模地震の発生は現実的なリスクとして想定されています。
実際に災害が起きれば、高層ビルでの長周期地震動による被害や、子どもを持つ従業員の帰宅希望、在宅勤務中の自宅での安全確保など、企業や従業員が直面する課題は多岐にわたります。
そのため企業は、従業員一人ひとりが適切に行動できるよう、防災研修を通じて知識と意識を高める必要があります。日頃の啓もう活動こそが、従業員の安全と事業継続につながります。
BCP策定・防災計画作成のアドバイス
企業が災害に備えるには、法令(東京都帰宅困難者条例、民法の善管注意義務、災害対策基本法など)を踏まえた防災計画の作成が不可欠です。
防災計画には、下記のような具体的なルールを盛り込む必要があります。
- 3日間の社内待機ルール
- やむを得ない場合の帰宅申請書の運用
- 災害対策本部による従業員の所在把握と行動制限
さらに、ショールームなど来客対応拠点を持つ企業は、お客様への対応方針も事前に計画やマニュアルに明記しておくことが重要です。これにより、災害時の混乱や不適切な対応を防ぎ、企業の信頼を守ることができます。
防災計画は、従業員とお客様の安全を守り、事業を継続するための基盤です。自社の実情に合わせて、わかりやすく実行可能な計画を策定しましょう。
防災観点でのレイアウト設計
オフィスのレイアウト設計では、快適さや業務効率に加えて「防災の視点」を取り入れることが欠かせません。大規模地震などが発生した際、家具の転倒や書類の散乱、避難経路の塞がれといった事態が、従業員の安全や事業継続に大きな影響を及ぼします。
例えば下記のような、日常的なオフィス設計の段階でリスクを減らす工夫が求められます。
- 背の高い収納家具は壁や床に固定する
- 通路は十分な幅を確保する
- 非常口までの導線を常に確保する
- 避難スペースや備蓄品の設置場所を考慮する
防災を意識したレイアウトづくりは、万が一の被害を最小限に抑えるだけでなく、従業員に安心して働ける環境を提供し、企業の信頼や事業継続力を高めることにつながります。
防災備蓄品の提案・販売

大規模災害が発生した際には、交通機関が麻痺し、多くの人が帰宅困難になることが想定されます。そのため企業には、従業員が安全に移動できるよう「帰宅支援セット」を備えることが求められます。
数ある備蓄品の中でも特に重要なのが、LEDライトと防塵用マスクです。夏場に地震が発生した場合、日中の移動は熱中症の危険があるため、夕方以降の暗い時間帯に移動せざるを得ません。そこで視界を確保するLEDライトは必須です。
また、2030年までは建物の解体などに伴うアスベスト飛散のリスクも残っており、防塵用マスクの備えが不可欠です。
従業員の安全を守り、安心して行動できる環境を整えるために、防災備蓄品の計画的な導入をご検討ください。
まとめ
BCP(事業継続計画)とは、災害や事故などの緊急事態に備え、事業を中断させずに継続、または早期復旧させるための計画です。これは、売上損失や顧客離れを最小限に抑えるだけでなく、従業員の安全確保、企業の社会的信頼、そしてブランド価値を守る上でも不可欠です。
自然災害の発生やパンデミックの脅威にさらされている現在、適切なBCPの策定は企業として必須といえます。人・モノ・カネ・情報といった資源を守るためにも、いざという時のために平常時から備えておきましょう。
BCPは、一度策定したら終わりではありません。日々変化する状況に合わせて、定期的な訓練と見直しを通じて継続的に改善していくことが極めて重要です。
しかし、初めから完璧な計画を目指す必要はありません。まずは自社にとっての最優先事業を特定し、できる範囲で段階的に策定していくのが効果的です。計画を実際に運用しながら、徐々にその範囲と精度を高めていきましょう。