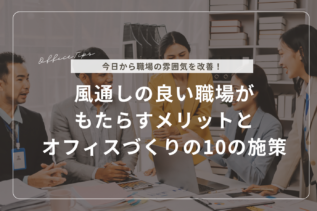従業員にとって働きやすく、生産性を上げる方法の1つに「フレックスタイム制度」の導入があります。
この記事では、フレックスタイム制度の導入を検討している企業向けに、仕組みやメリット・デメリット、実施する際の注意点などを解説します。
目次
フレックスタイム制度とは?ハイブリッドワークも解説
フレックスタイムとは、従業員自身が勤務時間をある程度自由に設定できる制度です。労働者は仕事と⽣活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
ここからはフレックスタイム制度がどのような仕組みなのか、具体的に見ていきましょう。
フレックスタイム制度の仕組み
これまでの一般的な企業では、「9時始業、18時終業」といった固定時間制を採用していました。一方のフレックスタイムの場合、従業員が自由に始業・終業時間を決めて働くことが可能です。
ただし、すべて自由に決められるわけではありません。フレックスタイム制度では、法定労働時間を守った上で、「コアタイム」「フレキシブルタイム」というルールに従い出勤します。
コアタイムとは、従業員が必ず出勤すべき時間帯のことです。コアタイムの設置は必須ではありませんが、業務やコミュニケーションを円滑にするため、設置する企業が多いようです。コアタイムを設けない場合は「スーパーフレックス制度」と呼びます。
フレキシブルタイムとは、コアタイムの前後に設ける、従業員が自由に出退勤できる時間帯のことです。
ハイブリッドワークとは?
働きやすい環境を整える施策として、フレックスタイム制度以外に「ハイブリッドワーク」という制度もあります。
ハイブリッドワークとは、テレワークとオフィスワークを組み合わせ、柔軟に場所を変えながら働くスタイルです。コロナ禍でテレワークが推進されたことから、ハイブリッドワークが注目されるようになりました。
ハイブリッドワークを導入することで、生産性アップやワークライフバランスの向上など、フレックスタイム制度とほぼ同じメリットを得ることができます。
フレックスタイム制度のメリット・デメリット
フレックスタイム制度にはメリット・デメリットがあります。メリットが多いイメージの制度ですが、デメリットも考慮したうえで運用しましょう。

メリット①:従業員満足度の向上
フレックスタイム制度では、ラッシュ時間帯を避けて快適に通勤したり、子どもの送迎をしてから出勤したりなど、柔軟な対応が可能です。さまざまな都合に合わせて勤務時間を調整できるため、従業員満足度の向上が期待できます。
また、育児や介護をしている人でも働きやすく、キャリアの障壁になりにくいでしょう。出産によって退職を避けられなかった場合でも、フレックスタイムなら働き続けることができ、離職率の低下にもつながります。
メリット②:残業時間の削減
時期によって繁忙期・閑散期がある企業は多いでしょう。繁忙期はどうしても時間外労働が増え、残業代もかさみます。フレックスタイム制度は、繁忙期の残業時間削減にも有効です。
例えば夕方~夜の業務が増えるケースでは、遅めの出勤・退勤を推奨することで残業を減らせます。反対に閑散期は早めの退勤を促すなど、業務量に合わせた働き方が可能です。
メリット③:採用のアピールポイントになる
従業員の自由度が高いフレックスタイム制度は、多くの求職者から好意的に受け取られます。フレックスタイムを導入していることは、採用時に大きなアピールポイントになるでしょう。
人材確保に苦慮する企業が多いなか、フレックスタイム制度をアピールすることで他社との差別化も可能です。その結果、優秀な人材の確保にもつながります。
デメリット①:勤怠管理が複雑化する
従業員の勤務時間が定まっていないフレックスタイムでは、勤怠管理が複雑になります。遅刻・早退や休憩の管理、時間給の計算方法などの規定から見直す必要があるでしょう。
勤怠管理ができていないと、知らぬ間に従業員に過重労働をさせてしまうといったリスクが生じます。
デメリット②:光熱費が増加する
フレックスタイム導入後は、フレキシブルタイムも含めてオフィスの稼働時間が増える傾向にあります。必然的に照明や冷暖房、パソコンなどの使用時間が増え、光熱費はかさむでしょう。エコな電化製品を導入するなど、電気代を節約する工夫が必要です。
デメリット③:従業員同士のコミュニケーションが不足する

フレックスタイム制度によって、従業員はそれぞれ異なる時間に出退勤します。また、ハイブリッドワークであれば出社しない従業員もいるでしょう。
従業員同士の顔を合わせる時間が減るため、どうしてもコミュニケーションが不足しがちになります。その結果、情報の共有漏れや、認識の齟齬が生まれるリスクがあります。
デメリット④:顧客への対応がしにくくなる
フレックスタイム制度の企業では、顧客対応が難しくなる恐れがあります。例えば、担当者が出勤前のフレキシブルタイムにトラブルが起きた場合、対応できないかもしれません。
こうした問題を避けるため、コアタイムを設定するなどして従業員が必ずいる時間を作り、顧客に周知すると良いでしょう。
企業がフレックスタイム制度を導入する方法と注意点
ここでは、実際にフレックスタイム制度を導入する方法をご紹介します。 会社がフレックスタイム制度を導入する際、以下の要件を満たさなければなりません。
1.就業規則等で規定すること
2.労使協定で所定の事項を定めること
就業規則には、「始業・終業時刻を従業員の決定に委ねる」旨を記載しましょう。 労使協定では、以下の事項を定める必要があります。
・対象となる労働者の範囲
・清算期間
・清算期間における総労働時間
・標準となる1日の労働時間
・コアタイムとフレキシブルタイム(任意)
出典:厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
注意点
フレックスタイム制度を導入する際はいくつかの注意点もあります。先述のデメリットも考慮し、適切に対応することを心掛けましょう。
特に注意したいのは、従業員同士のコミュニケーション不足です。チャットツールやビデオ会議ツールを活用し、コミュニケーションを円滑に行いましょう。
また、フレックスタイム制度はあくまでも従業員自身が自由に始業・終業時刻を決められる制度です。基本的に、上司が始業・終業時間を指定できない点にご注意ください。
フレックスタイムやハイブリッドワークはオフィス環境が鍵
フレックスタイムやハイブリッドワークを導入したい場合、制度に適したオフィス環境を整備する必要があります。
オフィス環境を整える
フレックスタイムやハイブリッドワーク行っている企業では、決まった席を割り当てないフリーアドレス制を採用している企業も多いです。フリーアドレスの場合、その日の出勤時間や業務内容に合わせて席を決めることができます。
また、オフィス設計によって、情報共有やコミュニケーションを促進することも可能です。例えば、会議室の増設、リフレッシュスペースの確保などが有効でしょう。
システム面ですべきこと

導入と同時にシステム面も整備する必要があるでしょう。例えば、勤怠管理システムを利用することで、従業員の出退勤の状況を把握できます。
リモートワークの従業員が増える場合は、オフィスのセキュリティ対策にも注意してください。目的によっては、パソコン・Wi-Fiルーターの貸与管理や、セキュリティーソフトの購入が必要となります。 また、従業員へのセキュリティ研修もあわせて実施しましょう。
フレックスタイム制度を活かすオフィスはリリカラまで
フレックスタイム制度を導入する場合、鍵を握るのが「オフィス環境の整備」と「デジタルツールの活用」です。 リリカラは、フリーアドレスへの移行をはじめとする豊富な実績から、オフィスリニューアルを支援しています。また、ご要望に合わせた最適なICTツール・スマートオフィスを提案します。フレックスタイムやハイブリッドワークを導入したい場合は、お気軽にご相談ください。
■多様な働き方ができるオフィスデザイン

フレックスタイムとオフィス環境改善はセット
フレックスタイム制度は、従業員1人ひとりが自由に始業・終業時刻を定められる、裁量の大きい働き方です。時間に縛られるストレスが減ることから、業務効率化や離職率の低下などの効果が期待できます。
さらに自由度の高い働き方を求める場合は、ハイブリッドワークの導入も検討しましょう。フレックスタイムやハイブリッドワークの導入に向けて最適なオフィス環境を実現したい場合は、ぜひリリカラにご相談ください。