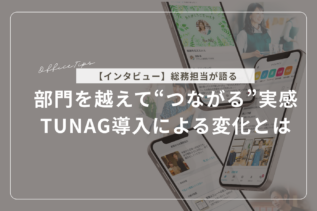社内でスムーズに仕事を進めるためには、コミュニケーションの質がとても大切です。
しかし、情報の伝わり方や意思疎通にズレが生じる「ディスコミュニケーション」は、どんな職場でも起こりうる課題です。このような状態が続くと、業務の効率が下がったり、チームの信頼関係が損なわれたりしかねません。
本記事では、「社内での会話が減ってきた」「部署間の連携がうまくいっていない」といった課題を感じている方に向けて、ディスコミュニケーションの原因や背景、そして改善のための具体的な対策をご紹介します。

社内での交流を促す具体的なコミュニケーション施策を事例を交えてご紹介。空間づくりだけでなくソフト面の施策が知りたい方はぜひご参考ください。
ディスコミュニケーションとは
ディスコミュニケーションとは、英語の「dis」(否定や不足を意味する接頭辞)と「communication」(コミュニケーション)を組み合わせた造語で、意思伝達がうまく行われていない、もしくは十分に機能していない状態を表します。
例えば、重要な情報が共有されないまま仕事が進んだり、伝えたい内容が相手に正確に伝わらなかったりする状況は、ディスコミュニケーションの典型例です。
このような問題を放置すると、業務の効率が落ちたり、チーム内の信頼関係が損なわれるリスクが高まるため、早期に課題を把握し、適切な対策を行うことが求められます。
ミスコミュニケーションとの違い
「ディスコミュニケーション」は、似た意味で使われやすい「ミスコミュニケーション」と混同されがちです。どちらも職場のコミュニケーションを妨げる原因ですが、根本的な問題は異なります。響きは似ていますが、意味に明確な違いがあるため、正しく使い分けることが大切です。
| 項目 | ミスコミュニケーション | ディスコミュニケーション |
|---|---|---|
| 意味 | コミュニケーションは行われているが、伝達内容にズレや誤解がある | そもそもコミュニケーションが行われていない |
| 結果 | 誤解やすれ違いが起こる | 情報不足による混乱・孤立などを招く |
| 例 | 指示の意図が伝わらず、別の行動をとってしまう | 会議の予定が共有されておらず、参加できない |
ミスコミュニケーション
意味:コミュニケーションは行われているが、伝達内容にズレや誤解がある
結果:誤解やすれ違いが起こる
例:指示の意図が伝わらず、別の行動をとってしまう
ディスコミュニケーション
意味:そもそもコミュニケーションが行われていない
結果:情報不足による混乱・孤立などを招く
例:会議の予定が共有されておらず、参加できない
ディスコミュニケーションが発生する原因
ではなぜ、職場ではコミュニケーションのすれ違いが起こってしまうのでしょうか。その要因となりやすい環境やケースについてご紹介します。
コミュニケーションがスムーズにいかない環境
職場の環境そのものがコミュニケーションをとりにくい状況にある場合、ディスコミュニケーションが発生しやすくなります。
例えば、業務に必要な会話以外の雑談やちょっとしたコミュニケーションがしづらい、社員全員が忙しく声をかけにくい、あるいはテレワークが中心で気軽なやり取りや交流の場がない、といったケースです。
こうした職場環境では、従業員同士のつながりが薄くなり、業務上の疑問や相談ごとがあっても話しかけづらくなるため、担当者が問題を一人で抱え込みがちです。
特に、「ちょっとした会話すらしにくい」と感じる場合は、すでにディスコミュニケーションが職場で進行している可能性が高いといえるでしょう。
伝えたつもり・伝わったはずという思い込み
「言ったから伝わっているはず」「聞いていたから理解しているだろう」という思い込みが、職場におけるディスコミュニケーションの原因となることがあります。
例えば、会議で一度説明した内容を全員が把握していると思い込み、フォローや確認を行わないケース。また、チャットで共有したつもりでも、相手が見落としていたり、意図を正しく理解していなかったりすることもあります。
こうした「伝えたつもり」「伝わったはず」といった思い込みが積み重なると、認識のズレやミスが発生しやすくなり、業務に支障をきたす恐れがあります。
特にテキストコミュニケーションが中心の職場では、言葉のニュアンスや温度感が伝わりづらく、すれ違いが起きやすくなるため注意が必要です。
ディスコミュニケーションを防ぐためには、情報の伝達後に確認のプロセスを設ける、相手の理解を前提にしないといった意識が欠かせません。
情報を省略・簡略化しすぎる
伝えるべき情報を省略したり、必要以上に簡略化したりすると、相手に正しく意図が伝わらず、ディスコミュニケーションを招く原因になります。
話の背景や文脈をある程度共有している相手であれば問題が起きにくいものの、特に相手が初めて取り組む業務や慣れていない分野に関しては、情報が不十分になりがちです。
また、指示語(「それ」「あれ」など)を多用したり、英語の略語や業界特有の用語を使いすぎたりすることで、内容の理解を妨げてしまうこともあります。
これは、相手が「わかっているはず」「知っているだろう」と思い込むことに起因しやすく、確認や補足を怠ることで、知らず知らずのうちに認識のズレが生まれてしまいます。
相手の理解度や前提知識に応じて、必要な情報を丁寧に伝える姿勢が、ディスコミュニケーションの防止には不可欠です。
会話しにくい状態が発生している
職場で会話がしにくい環境が続いている場合、それはすでにディスコミュニケーションが進行している兆候といえます。
完全に個人で完結する業務以外では、同じ部署のメンバーや上司とのコミュニケーションが不可欠です。しかし、業務に必要な会話だけでなく、何気ない雑談や気軽なやり取りが減少すると、職場の連携が弱まり、やがて大きな問題へと発展するリスクがあります。
このような状況を放置せず、早期に課題を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

ディスコミュニケーションにより起こる弊害
職場でディスコミュニケーションが発生すると、次のようなさまざまな問題が起こる可能性があります。
意思疎通がしづらくなる
ディスコミュニケーションの状態になると、意思疎通が難しくなることがあります。何気ない会話が減ることで、メンバー同士がお互いの人柄や考え方を理解しにくくなり、意思疎通の難しさがさらに深刻化する悪循環に陥ります。
チームでの業務には、メンバー間の相互理解が欠かせません。しかし、雑談や日常的なコミュニケーションが取りづらい環境では、基本的な意思疎通すらも円滑に行えなくなり、結果としてチームの連携力や生産性に悪影響を及ぼします。
業務上のトラブルが発生しやすくなる
社内にディスコミュニケーションが広がると、業務上のトラブルが起こりやすくなります。従業員間で意思疎通が不十分だと、業務内容の認識にズレが生じ、ミスや誤解が積み重なることが原因です。
こうしたトラブルは、初期段階では小さな問題に見えることも多いものの、放置すると業務効率の低下や品質の悪化を招き、最終的には業績の悪化や取引先からの信頼失墜につながるケースも少なくありません。
そのため、ディスコミュニケーションの兆候を見逃さず、早期に対策を講じることが企業の健全な成長には不可欠です。
業務効率・生産性の低下
ディスコミュニケーションが継続している職場では、情報共有の遅れや誤解が増え、業務効率や生産性が低下します。情報の伝え漏れや勘違いが増えると、納期に遅れたり、成果物のクオリティが下がったりすることも珍しくありません。結果として、仕事全体のパフォーマンスが落ちてしまいます。
また、雑談やちょっとしたコミュニケーションが減ると、従業員同士の意見交換や情報共有の機会も減り、新しいアイデアや改善案が生まれにくくなります。
そのため、イノベーションのチャンスが減り、会社全体の生産性アップにもブレーキがかかってしまうのです。
エンゲージメントの低下
職場にディスコミュニケーションが浸透してしまうと、従業員のエンゲージメント低下が大きな問題となります。コミュニケーションが不足すると、職場に対して不満や嫌気を感じる従業員が増え、企業に対する愛着ややる気が薄れてしまうことが多いです。
その結果、生産性の低下や離職率の上昇といった悪影響が現れるケースも少なくありません。
こうした観点からも、ディスコミュニケーションを早期に解消し、良好なコミュニケーション環境を整えることが重要だといえます。
企業の評価や評判が悪化する
ディスコミュニケーションが日常的に続くようになると、企業の評価や評判にも悪影響が及びます。
従業員同士のコミュニケーション不足は、納期遅れや品質低下といったトラブルを引き起こし、結果的に取引先からの信頼を失うリスクが高まります。こうした状況は、営業機会の損失にもつながりかねません。
また、職場の雰囲気が悪いと感じた従業員が、ネットの掲示板やSNSでその不満を発信することもあります。そうした声が拡散されると、求職者の応募が減少し、優秀な人材の確保が難しくなるケースも少なくありません。
さらに、「ブラック企業」というイメージが外部に広まると、取引先との関係だけでなく、企業の社会的な信用やブランド価値にも深刻なダメージを与える可能性があります。
コミュニケーションの質を高める7つの方法
ディスコミュニケーションが起こると、さまざまな悪影響や問題が生じます。
そうした状況を防ぐためにも、職場でディスコミュニケーションの兆候を感じたら、早めに対策を講じることが大切です。
コミュニケーションの課題を明確にする
まずは、職場のコミュニケーションにどんな課題があるのかをしっかり洗い出しましょう。課題を明確にすることで、優先的に改善すべきポイントが見えてきて、ディスコミュニケーションの解消に効果的です。
具体的には、まず「どの部署やメンバー間のコミュニケーションに問題があるのか」を把握し、次に「どのようなコミュニケーションの課題があるのか」を詳しく確認します。
こうして、「誰と誰の間で、どんなコミュニケーションの問題が起きているのか」がわかれば、適切な対策を立てやすくなります。
効果的な伝え方のポイント
ディスコミュニケーションを防ぐには、相手にわかりやすく伝える工夫が欠かせません。「伝えたつもり」「伝わったはず」という誤解を避けるためにも、意識して取り組むことが重要です。
具体的には、次のポイントに注意しながら、相手に伝わりやすいコミュニケーションを心がけましょう。
- 相手の理解レベルに合わせて、言葉遣いや伝え方を工夫する
- 簡潔に話すことを心がける
- 話す前に、伝えたい内容や順序を整理する
- 話し方や声のトーンに気を配る
- まず結論を伝える
- 抽象的な表現を避け、具体例を交えて説明する
- 質問を使って相手の理解度を確認する
- 伝えた内容が正しく伝わっているか、フィードバックを求める
- 図やイラストなどの視覚的な情報を活用する
これらの伝え方の工夫を意識することで、相手とのコミュニケーションがよりスムーズに進むようになるでしょう。
良い対話は“聞く姿勢”から始まる
ディスコミュニケーションを防ぐためには、相手の話にしっかり集中することが重要です。作業をしながらやパソコンに向かいながらの会話では、相手の話が頭に入りにくくなり、認識のズレが生まれやすくなります。
コミュニケーションの誤解を避けるためにも、一旦作業を中断し、会話に集中する姿勢を心がけましょう。さらに、頷いたり、話を繰り返したり、質問をするなどのリアクションをとることで、意思疎通がスムーズになります。
こうしたやり取りによって、相手も自分の話がきちんと伝わっていると感じられるようになります。
不明点はしっかり確認する
会話の中で不明点があれば、そのままにせずその都度しっかり確認することが大切です。
発信者の「伝えたつもり」「伝わったはず」という思い込みから生じる認識のズレを防ぎ、ディスコミュニケーションの改善につながります。
特に業務の流れや納期など重要なポイントで確認が不足すると、業務効率の低下や生産性の悪化を招く可能性があります。
こうした確認を積み重ねることでコミュニケーションの量も増え、会話がしにくい職場の雰囲気も徐々に改善していくでしょう。
コミュニケーションが取りやすい職場環境を作る
ディスコミュニケーションを防ぐためには、コミュニケーションがしやすい環境づくりが欠かせません。
特にテレワークが普及している企業では、対面でのやり取りが減り、コミュニケーション不足から問題が起きやすくなっています。
こうした場合は、定期的な社内イベントの開催や、会議の冒頭にアイスブレイクとして雑談の時間を設けるなど、参加者の緊張をほぐす工夫が効果的です。
また、上司と部下が1対1で話せる面談の場を設けたり、先輩社員が若手社員をサポートするメンター制度を導入するのも有効な手段です。
より詳しいオフィス環境や働き方の改善案については、下記のコラムもぜひご覧ください。

信頼関係は日々の姿勢から
ディスコミュニケーションを防ぐためには、日頃から信頼関係を築く努力が欠かせません。
仕事の場では人と人との関わりが避けられないため、相互の信頼がスムーズなコミュニケーションの基盤となります。
相手を信頼し、自分も信頼されるために、次のようなコミュニケーションを意識して信頼関係を育んでいきましょう。
- 相手の話をしっかり聞き、理解しようと努める
- 相手の気持ちに寄り添い、共感を示す
- 適度に自分のことも話し、距離感を縮める
- 約束をきちんと守る
- 言葉に責任を持ち、言ったことは必ず実行する
- 小さなことでも感謝の気持ちを伝える
信頼関係は、一朝一夕で築けるものではありません。
日々の一貫した行動を積み重ねることで、長期的に強固な信頼関係を築いていくことが大切です。
効果的なコミュニケーションツールを活用する
ディスコミュニケーションを解消するために、職場のコミュニケーションを円滑にするツールの導入を検討しましょう。
例えばビジネスチャットを使えば、メールよりも気軽に連絡が取れるため、「出先でメールを送るのが手間」という場合でも簡単にやり取りができます。
また、メールだと全体のやり取りの流れが見えにくくなりがちですが、ビジネスチャットならメッセージ履歴を簡単に確認できるのも大きなメリットです。
さらに、社内SNSで上司と個別チャットができる環境があれば、業務報告以外にも気軽に相談や報告が可能になります。
上司もすべてにコメントする必要はなく、Facebookの「いいね」やLINEのスタンプのような簡単なリアクションで十分です。

オフィスのレイアウトを変える
ディスコミュニケーションを解消するために、オフィスのレイアウトを工夫することも効果的です。
例えば、デスクをジグザグに配置したり、オフィス内を自由に回遊できるレイアウトにすることで、従業員同士の視線が自然と交わりやすくなります。
これにより、部署の垣根を越えたコミュニケーションが促進され、職場の連携が深まるでしょう。


またオフィス内にカフェスペースや休憩スペース、オープンなミーティングスペースを設けるのもおすすめ。従業員間の偶発的なコミュニケーションの増加や、コミュニケーションの活性化に役立つでしょう。


まとめ
ディスコミュニケーションとは、コミュニケーションが十分に機能していない状態を指します。職場でこのような状況が起こると、業務のスムーズな進行が妨げられたり、従業員の仕事への意欲が低下したり、さらには企業のイメージダウンにもつながる可能性があります。
もしディスコミュニケーションが見られる場合は、まずは問題点をはっきりさせることが大切です。そのうえで、わかりやすい伝え方を心がけ、不明点はこまめに確認するようにしましょう。加えて、コミュニケーションツールの導入やオフィス環境の見直しも効果的な解決策となります。
リリカラではディスコミュニケーションを防ぐオフィス構築のご支援が可能です。オフィスの新設や移転、リニューアル時には、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

社内での交流を促す具体的なコミュニケーション施策を事例を交えてご紹介。空間づくりだけでなくソフト面の施策が知りたい方はぜひご参考ください。