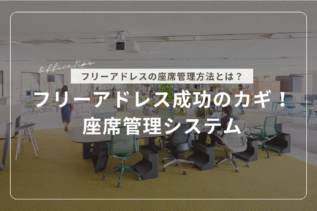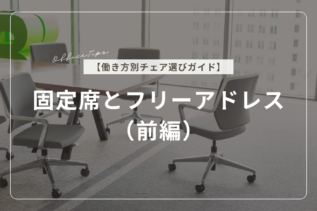フリーアドレスの導入を検討する際、快適な働き方を実現するためには「どのようなデスクを選ぶか」が重要なポイントになります。
この記事では、フリーアドレスに適したデスクの種類や選び方をわかりやすく解説するとともに、実際にリリカラが手掛けた導入事例もご紹介します。フリーアドレスの導入を検討しているご担当者の皆さまは、ぜひオフィスづくりのヒントとして参考にしてください。

オフィスのフリーアドレス化を成功に導く4つのステップをまとめたフリアド導入ガイドブックです。
フリーアドレスとは
フリーアドレスとは、執務スペースの中に個人の固定席を作らず、様々なデスクを設置してその時に利用可能な席を自由に選んで働くワークスタイルのことをいいます。
従来の固定席とは異なり、部署の垣根を越えて複数人でデスクやスペースを共有します。
フリーアドレス導入が増えている背景
フリーアドレスの導入が広がっている背景には、働き方の多様化が進んでいることが挙げられます。リモートワークやハイブリッドワークが定着しつつある現在、オフィスは「全員が毎日出社する場」から、「必要なときに集まり、交流や協働が生まれる場」へと役割が変化しています。こうした流れの中で、座席を固定せずに自由に働けるフリーアドレスは、柔軟な働き方や省スペース化を可能にする手段として注目されています。
企業側はリモートワークやハイブリッドワークの導入によって、オフィスに全員分の席を設置するのがスペースの無駄と感じるようになり、これがさらにフリーアドレスの増加に拍車をかけました。
現在ではIT企業を中心に、メーカーや官公庁(環境省・総務省)などでもフリーアドレスの導入が進められています。
フリーアドレス化するメリット・デメリット
フリーアドレス化するメリットは、社内のコミュニケーションが活性化すること。毎日違う席に座るので、普段交流のない部署や他チームのメンバーとの交流が促進されます。
さらに座席と人が結び付いていないので、組織変更や急な人員増加にもレイアウト変更せずに対応可能に。出社比率に応じて座席数を減らせるので、オフィススペースの有効活用もできます。
一方で誰がどこにいるか一目で分からないので、報連相がスムーズにいかない、チーム内のコミュニケーションが不足する、部下の管理が難しくなるといったデメリットが生じます。また出社する度に席を探す手間がかかり、自分の荷物ごと移動しなければならないなど、個々の負担が大きくなる点もフリーアドレスのデメリットです。

フリーアドレスの向き不向き
フリーアドレスには導入に向き・不向きの部署があります。それ故にフリーアドレスをすべての部署・部門に導入せず、最適な部署のみに導入するケースが多々あります。
フリーアドレスに向いているのは、外出する時間が多い営業部門や会議、ミーティングが多い企画部門など。またノートパソコンやタブレットのみで業務ができる職種にも向いています。
一方で総務・人事・経理など社内の人とのやり取りが多い部門は、固定席の方が向いています。またコーポレート部門や営業アシスタントなども同様です。
紙媒体の書類を多く扱う部門や、専用機材を使って設計などをする部門、セキュリティレベルが高い書類を扱う職種は、席を異動することで業務効率の低下や情報漏洩のリスクが高まるため、フリーアドレスに不向きです。

フリーアドレスに適したデスクの種類と特徴
ここではフリーアドレスに適したデスクの種類や特徴を紹介していきます。導入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
増結・連結型デスク


フリーアドレスに適したデスクの多くは、増結や連結が可能な機能を持っています。拡張できるサイズは商品によって異なるものの、8,000~10,000mm程度まで拡張可能です。
増結・連結可能なデスクを導入することで、単に個人ワーク用のデスクを並べるよりもデスクの脚が邪魔にならずすっきりします。
またデスクの脚が気にならないので、人数の増減に応じたスペースの有効活用が可能に。
個人ワーク用デスクより割安なので、導入コストを抑えられる点もメリットです。
導入時には、形を変更したいときにスムーズに組み替えられるかのチェックが必要。レイアウト変更時に専門業者への依頼が必要な商品もあるので、事前に確認した上で導入するようにしましょう。
キャスター付きデスク


デスクの脚にキャスターが付いている一番のメリットは、使用する人自身で移動ができる点。その特徴を生かして、ミーティング用のテーブルとしての利用がおすすめです。
レイアウト変更や移動に対応できるよう、電源などの配線計画をあらかじめ行っておくことで、さらにフレキシブルな活用ができるでしょう。

昇降デスク・スタンディングタイプ


最近ではデスクの天板の高さを変えられる昇降デスクや、立って使うスタンディングタイプのデスクもあります。
昇降デスクは業務内容や気分によって、立ったり座ったりして使えるのが特徴。また健康志向の高まりから、運動不足の解消に効果的で身体への負担を軽減できるスタンディングタイプを導入するオフィスも増えています。
立って仕事をするのは、集中力を高めたり、リフレッシュ効果も期待できます。近くを通りかかった社員と同じ目線になるので、コミュニケーションの活性化も期待できるでしょう。

フリーアドレスに適したデスクの選び方
フリーアドレスの導入を決めた場合、どのような点に留意してデスクを選べばいいのでしょうか。こちらではフリーアドレスに適したデスクを選ぶ際のポイントについて解説していきます。
座席設定率(数)を決める
フリーアドレスを導入する場合には、座席設定率(数)を決めるところから始まります。座席設定率は、フリーアドレスとして使用する席をフリーアドレス対象者数に対して、何パーセント(何席)準備するのかを決めるために必要です。
例えばフリーアドレス対象の社員が100名いた場合、フリーアドレス席を60席準備したとすると、座席設定率は60%(60席)となります。この座席設定率によってデスクの数やレイアウトを決定するので、事前によく検討しておきましょう。
座席設定率の設定方法は、職種ごとに分ける場合や、職種に関係なく一律にする場合など、企業によってさまざまです。フリーアドレス導入の目的や、働き方に合わせて設定するといいでしょう。
1人あたりのデスクスペースを確保する
デスクを導入する場合、1人あたりのデスクスペースを確保するのがポイント。一般的に1人当たりの作業スペースの目安は、幅1,000mm〜1,200mm×奥行600~800mmといわれています。そして通路幅は、椅子の前後の可動域9000mm~とします。
1人当たりのスペースが狭すぎると作業がしにくくなり、オフィスへの満足度が低下することにつながります。逆に必要以上に広くスペースを取ると、オフィススペースを効率的に使えません。
デスクを導入するときには、1人あたりのデスクスペースを考え、執務スペースの中でどれくらいの面積を割り当てるのかを利用シーンと併せて検討しましょう。
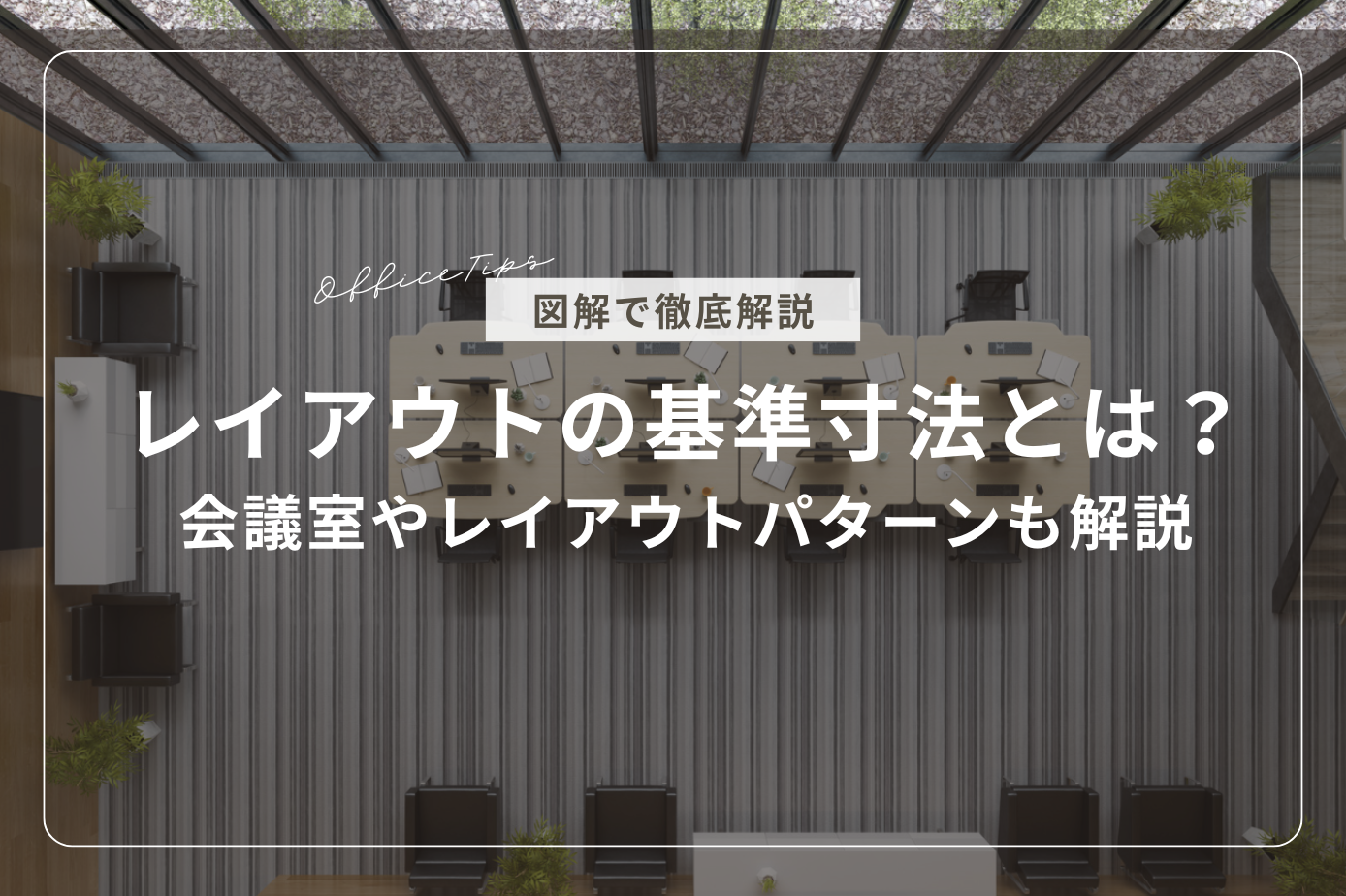
固定席が必要な社員の有無を考慮する
部署や部門によっては、フリーアドレスに向かない場合があります。そうした固定席が必要な社員の有無を考慮して、デスクを導入するようにしましょう。
フリーアドレスは、部署や部門の垣根を超えて社員同士のコミュニケーションが活性化されるのが大きなメリットです。しかし一方で個人ワークやリモート会議などに集中しにくい環境を作ってしまうことも。
また紙媒体の書類を多く扱う部門では、固定席にした方が業務効率が低下しません。このような課題に対して、柔軟に対応していくことがデスク導入のポイントです。
まずは固定席が必要な社員の数を明らかにし、そのような部署は固定席を維持できるようにしましょう。さらに個人ワークやリモート会議ができる、個人ブースやWeb会議ブースの設置も検討してください。

書類や私物の保管場所を確保する
フリーアドレス化によって、どの席でも自由に仕事ができる環境になりますが、書類や私物の保管場所がないと、いちいちそれらを持って移動しなければなりません。かえって仕事がしにくくなったり、作業効率が低下する恐れがあります。
フリーアドレスの導入時には、こうした問題を改善するためにパーソナルロッカーやオープンワゴンの採用も検討しましょう。


パーソナルロッカーとは、オフィス内に設置する個人用収納庫のこと。フリーアドレスの場合、固定席のように個人の持ち物を置いておけるスペースがないので、個人で使用するノートパソコンや書類などを収納できるパーソナルロッカーがおすすめ。
またオープンワゴンは、PCバッグや通勤用バッグなどを収納したまま、キャスター付きで移動できたりデスクの下に収納できる点が便利です。

配線や収納などの機能性をチェックする
デスクの導入時には、配線や収納などの機能面もチェックしてください。とくにデスクの配線機能は、席を移動する度にノートパソコンやスマホの充電機器を接続する必要があるため、非常に重要です。
天板面の回線の種類には、コードホールタイプと配線カバータイプの二種類があります。コードホールタイプは天板面に電源タップや配線口が設けられているもの。配線カバータイプに比べると利便性はやや劣るものの、コストパフォーマンスが良いのが特徴です。
そして配線カバータイプは、開閉式のカバーがデスクの天板面についていて、配線作業がスムーズにできるのがメリット。見た目がスッキリとしていますが、コードホールタイプよりも価格が高めです。

自社のニーズに合う種類と機能を確認する
デスクの導入時には、自社のニーズに合う種類や機能があるか確認してください。一人当たりのデスクスペースを考慮したうえで、デスクの形状や昇降機能の有無、配線機能などをチェックしましょう。
例えば人数の増減にスムーズに対応したい場合は、増連結できるデスクがおすすめ。
また社員間のコミュニケーションを活発化させたいときは、移動しやすいキャスター付きデスクを選ぶといいでしょう。
集中して作業するスペースやWeb会議ができるスペースが欲しいときには、個人ブースなどを配置すると利便性がアップします。
全体のレイアウトや動線との相性を確認する
フリーアドレスにかかわらず、デスクの配置はオフィスでの働きやすさに直結します。とくにデスクのレイアウトは、オフィス内の動線と密接に関係するため、相性を確認したうえで導入しましょう。
この動線計画をないがしろにすると、かえってコミュニケーションが阻害されたり、人の移動が妨げられたりして働きにくいオフィスになってしまうこともあります。
導入目的に合わせてレイアウトを設計するほか、使用目的別にゾーニングするのもスペースの有効活用に効果的。
更にレイアウト時には、現場の社員の声を取り入れることも大切です。オフィス環境は社員の生産性やモチベーションに大きく影響します。働く人にとって最適なレイアウトになるよう、直接意見を聞くなどして現場の声を取り入れながら導入を進めましょう。

フリーアドレス導入事例
こちらでは、実際にリリカラが手掛けたフリーアドレスの導入事例を紹介していきます。こちらにもフリーアドレスのオフィス事例を紹介しています。フリーアドレスを採用する際には、参考にしてください。
明治アニマルヘルス株式会社様

こちらは12種類のデスクを導入した事例です。シンボルツリーを配置した円テーブルを中心におにぎり型のテーブル6人掛けのテーブル、ハイテーブルなどを用意しています。
他にもソファ席や昇降デスクもあり、視線の変化によるリフレッシュ効果やアイデアを生み出しやすくする効果が期待できます。
首都高アソシエイト株式会社様

部門の垣根を超えた交流がしづらく、働き方をアップデートできていなかったという課題を解消するために、フリーアドレスを導入した事例です。
部門間の交流を狙った6人掛けのロングテーブルや、集中作業に適した昇降デスクなど、フリーアドレスならではの状況に適した席を多数用意しました。
エプソン販売株式会社様

業務の特性に応じた3つのエリアに、19種類の座席を用意したフリーアドレス事例です。
それぞれのエリアにいる人の視線が交わらないよう、OAコーナーを配置して緩やかにエリアを区分け。また造作のカウンターデスクやハイテーブルなど、高さ違いの家具を組み合わせて、視線の分散を狙いました。
まとめ
コロナ禍をきっかけに広まったフリーアドレスには、メリット・デメリットの両面があります。部署ごとの業務内容や働き方に応じて、導入の可否を検討することが重要です。
フリーアドレスに対応したデスクには、増連結型やキャスター付き、昇降機能付きなど様々な機能や種類があります。自社のニーズに合う機能を備えた、レイアウトや動線との相性が良いデスクを選ぶようにしましょう。
実際にデスクを選ぶ際には座席設定数を決め、1人あたりのデスクスペースを確保したうえで、その後の運用も見据えて選ぶのがポイントです。
リリカラでは、これまで数多くのフリーアドレスのオフィスを手掛けてきました。
オフィス移転やリニューアルのご相談も承っていますので、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。