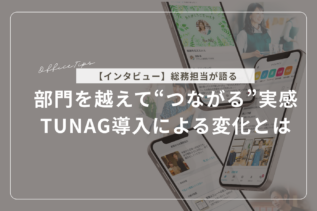「社員同士のコミュニケーションが少ない」「本音で意見を言い合える雰囲気がない」など、あなたの職場にそんな課題はありませんか?
これらの問題の根底にあるのは、「風通しの悪さ」かもしれません。本記事では、風通しの良い職場がもたらすメリットを解説するとともに、オフィス空間のデザインやレイアウトの工夫、そして今日から始められる10の具体的な施策を徹底的にご紹介します。
実際の成功事例や、意見を気軽に伝え合える仕組みづくりについても触れていますので、ぜひ今後の職場改善の参考にしてくみてください。

社内での交流を促す具体的なコミュニケーション施策を事例を交えてご紹介。空間づくりだけでなくソフト面の施策が知りたい方はぜひご参考ください。
目次
風通しの良い職場とは?
「風通しの良い職場」とは、年齢や役職にとらわれず、誰もがフラットな関係の中で自分の考えを気兼ねなく伝えられる職場のことです。「フラットな職場」や「オープンな職場」とも言い換えられ、社員同士で意思疎通がしやすく、意見交換が活発な職場のことを指します。
ただし、自由に意見できるといっても、何を言ってもよいという意味ではありません。組織のルールを踏まえ、互いに配慮しながら意見を交わすことで、真に風通しの良い職場が実現できます。
風通しの良い職場の特徴・要素
風通しの良い職場には共通した特徴や要素がいくつかあります。まずはそれらについて解説していきます。
社内や部署内のコミュニケーションが活発
社員同士や部署間で会話が活発に交わされていると、その職場は風通しが良いといえるでしょう。何か問題が発生しても気軽に相談できる環境であれば、情報共有や意見交換がスムーズに行えます。その結果、社員同士の信頼が高まり、ストレスも和らぎます。
社内でのコミュニケーションを盛んにするには、日々の挨拶や雑談が大切。
一見すると無駄話のように思われますが、風通しの良い職場にする上では欠かせません。

意見を言いやすい雰囲気がある
意見を気軽に伝えられる環境づくりも、風通しの良い職場に欠かせないポイントです。
良い意味で上下関係がフラットだと、役職や立場、年齢にかかわらず自分の意見を言いやすくなります。その結果、社員は主体性を発揮しながら、伸び伸びと働けるようになります。
このように職場に意見を言いやすい雰囲気があれば、問題が生じたときにも速やかに共有され、解決に向けた話し合いが迅速に行われるはずです。
上下関係にかかわらず意見を言いやすい職場環境にするには、お互いの呼び方を「○○(名字)さん」に統一するといった方法が有効です。
役職名をつけないことで、上司と部下の垣根を低くし、意見を言いやすい雰囲気づくりに役立ちます。
上司・部下・同僚間の人間関係が良好
風通しの良い職場では、上司や部下、同僚との関係性が円滑です。
お互いを認め合い、自然に助け合える環境があり、肩ひじを張らずに会話できるため、率直な意見交換がしやすくなります。
逆に強い口調で命令する、何を言っても否定される、成功をねたむ、失敗を責めるといった重い雰囲気の職場では、社員が委縮しストレスを感じてしまうでしょう。
風通しの良い職場をつくるには、人間関係を円滑に保つことが大切です。
心理的安全性が高い
風通しの良い職場では、心理的安全性が確保されていることも特徴です。心理的安全性とは、組織の中で、どの相手に対しても安心して意見や考えを発言できる状態のことです。
心理的安全性が高い職場では、自分の行動や発言によって、誰かに拒絶されたり、無視されたり、恥をかかされたり、責められるのではないかという不安がありません。
年齢や役職に関係なくアイデアや意見を出し合える環境が整っているので、新しいアイデアや提案が生まれやすくなります。さらに失敗を恐れずにチャレンジする姿勢も生まれるので、職場全体の活性化につながります。
企業の方針やルールが明確
風通しの良い職場は、会社の方針やルールがはっきりしていて、透明性が保たれています。
そのため、社員は適切な判断がしやすく、安心して業務に取り組むことができます。
つまり「暗黙の了解」や「ローカルルール」といった、よく基準が分からない不透明なルールがない職場です。
理不尽なルールや不文律で社員を叱責すると、会社への信頼が損なわれ、やる気も低下してしまいます。
逆に、方針やルールを明確に示すことで、社員の考え方を揃え、商品やサービスの品質を安定させる効果も期待できます。
やめたほうがいい職場の特徴
反対に、避けるべき「風通しの悪い職場」も存在します。
風通しの良い職場の特徴の要素がないほかに、下記のような特徴が当てはまります。
- 学びやスキルアップの機会が少ない
- プライベートや体調よりも会社優先の空気がある
- ハラスメントが放置されている
- 残業が常態化している
残業が常態化する理由には、社員同士の連携が取れていない、業務が効率的に進められていない、仕事の割り振りがうまく調整されていない場合などが考えられます。
このような職場は人間関係が良好でなく待遇や業務への不満が絶えないため、常に人手不足で、離職率が高いという特徴があります。
風通しの悪い職場の一部の問題は、社内で円滑なコミュニケーションを図ることで改善できる可能性があります。
上に挙げたような不満を抱えて退職する社員が多い場合には、職場の風通しが悪いサインの可能性も。職場内の環境を速やかに整えることが求められます。

風通しの良い職場がもたらすメリット
風通しの良い職場には、次のようなメリットがあります。
組織改善や課題発見が進みやすくなる
風通しの良い職場は、組織の課題に気づきやすく、改善が進みやすいというメリットがあります。
コミュニケーションを活発にすることで、多くの社員が議論に参加でき、結果として目的の実現に向けた組織改善が進みます。
また組織が目指す成果や目標達成のための課題、個人では気が付かなかった改善策が出されやすくなるのも風通しの良い職場のメリットです。
業務効率化と生産性の向上につながる
風通しの良い職場は、以下のようなメリットをもたらします。
- 業務効率・生産性の向上:社員のやる気が保たれ、組織全体のパフォーマンスが上がります。
- 目標・ビジョンの共有:今取り組むべきことが明確になり、社員全員が同じ方向を向いて仕事ができます。
- コミュニケーションミスの減少:情報共有が円滑になり、仕事上の行き違いが起きにくくなります。
- 問題解決の迅速化:仮にミスやトラブルがあっても、迅速に対応できるため、生産性や成果を損なわずに解決できます。
自分の意見がきっかけとなり組織が良い方向に進んでいると実感できれば、社員のモチベーションアップにつながります。
この好循環がさらに生産性の向上へとつながっていくのも、風通しの良い職場の大きなメリットです。
トラブルやミスへの迅速な対応ができる
トラブルを広げないためには、素早い情報共有や報告が大切です。
日頃から社員同士のコミュニケーションが盛んな職場では、何か問題が起きてもすぐに報告や共有がなされ、被害を抑えることができます。
さらに、情報をしっかり共有することで、小さなミスや不具合の芽を早期に発見し、事前に対策を取ることもできます。
スムーズに解決できる体制があれば、社員も安心して働けるでしょう。
社員の離職防止・満足度向上につながる
職場の風通しを良くすることは、社員の離職防止や満足度アップにつながります。
特に退職理由で多いのが人間関係に関する悩みです。
厚生労働省の「令和4年 雇用動向調査結果の概要」を見ても、前職を辞めた理由として「人間関係がうまくいかなかった」と回答した人が、性別や年代を問わず上位に入っています。
逆に言うと、人間関係が良好な職場なら、人材流出を防止できるだけでなく、社員の満足度を高める効果も期待できます。
職場の人間関係が円滑であることは、社員が会社に信頼や愛着を持ち、エンゲージメントが高まっている証といえます。意見を自由に発言できる雰囲気があれば、悩みや不満も共有されやすく、問題が早期に解決しやすくなります。
その結果、優秀な人材が突然離職するリスクを減らすことにもつながります。職場のコミュニケーションを活発にすることで、離職率の抑制が期待できるでしょう。
働く人の満足度やエンゲージメントが高まる
職場に対する満足感が上がることで、働きがいを感じる社員が多くなります。働きがいは社員の定着率を向上させるとともに、会社への愛着や信頼を示す「エンゲージメント」を高める効果も。
職場の風通しが良いと、社員がコミュニケーション不足からくる不安やストレスを抱えにくくなります。伸び伸びと働け、チームワークの機能によって仕事の成果も出しやすくなるでしょう。
充実感を持って毎日の仕事を進められる職場では、エンゲージメントが高い状態が保たれるだけでなく、社員が辞めにくく、安心して働き続けられる環境をつくることができます。
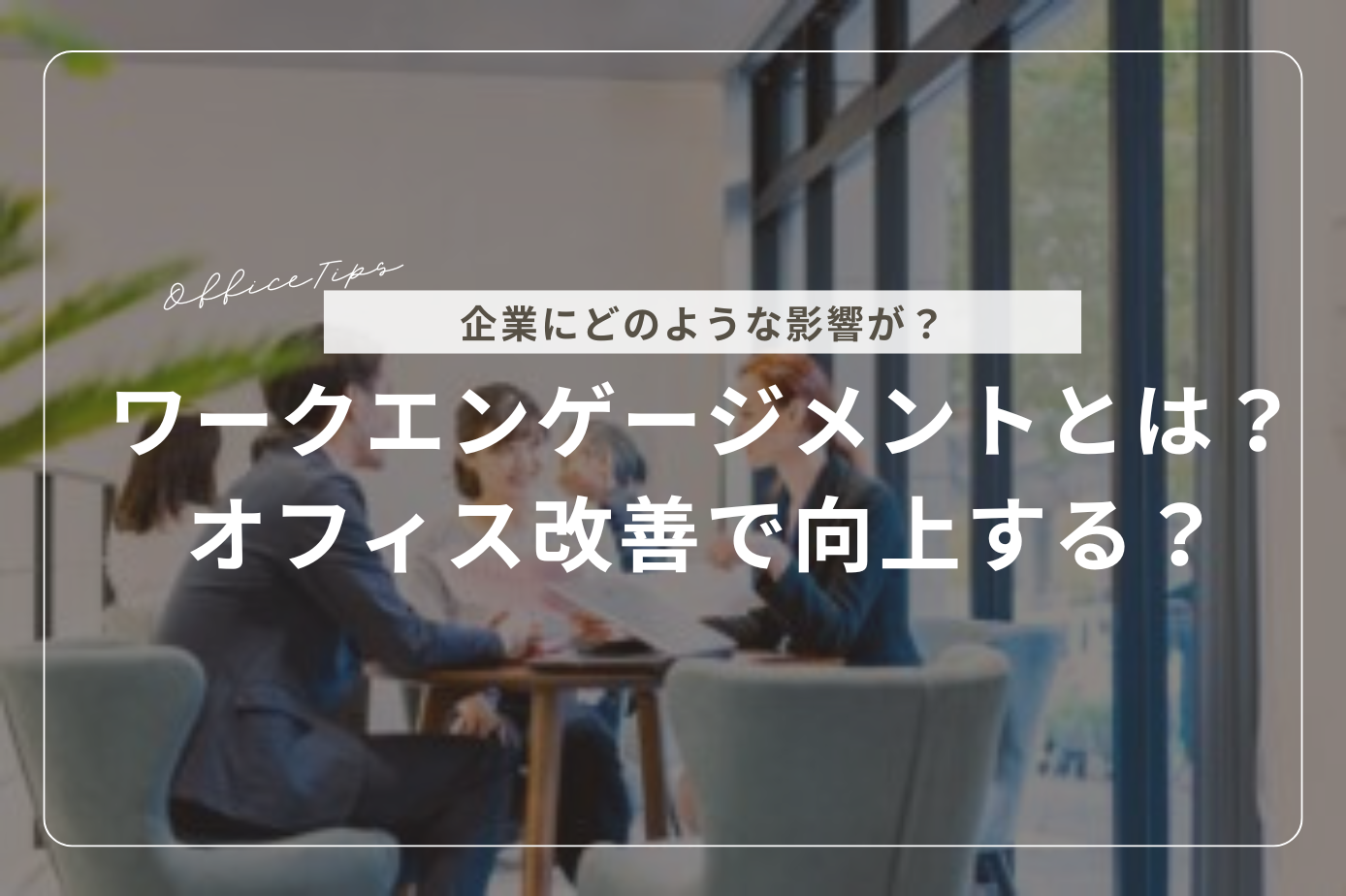
風通しの良い職場のデメリット・注意点
風通しの良い職場にはメリットがある反面、気をつけなければならない点やデメリットもあります。
人によりストレスを感じる場合がある
風通しの良い職場であっても、人によってはストレスを抱えることがあります。
職場には様々な性格やタイプの社員がいます。全ての社員が自由にコミュニケーションを取り、誰に対しても率直に意見を述べられるわけではありません。
中には人と話すのが得意でない人や、活発な意見交換を好まない人もいるでしょう。
そのようなタイプの人にとっては、風通しの良い職場が窮屈に感じられることもあります。
職場環境を整える際には、全員が率先して意見を出すわけではないことを理解し、発言しにくい人の意見も吸い上げられる工夫を心がけましょう。
緊張感がなくなる可能性がある
風通しの良さを重視しすぎて、誰もが遠慮なく意見を言える環境を作りすぎると、職場の適度な緊張感が薄れてしまうことがあります。
職場の緊張感がなくなると、勤務態度がルーズになったり仕事に対するメリハリがつけられなくなり、生産性が低下してしまう恐れがあります。
適度な緊張感を保つためには、個人の行動や意見を尊重しつつも、会社としての明確な目標や方針を持たせることがポイント。
上司と部下の関係はフラットであることが望ましいですが、親しいだけの関係にとどまるのは避けるべきです。上司は適切に指針を示し、メリハリのあるコミュニケーションを維持しましょう。
オープンなコミュニケーションを求めすぎると逆効果
風通しの良い職場を目指すあまり、全員にオープンなコミュニケーションを求めすぎると、かえって逆効果になることがあります。
オープンなやり取りは大切ですが、特に内向的な社員や自分のペースで働きたい人にとっては、強制されるとストレスや負担につながることもあります。
風通しの良い職場には、自然に会話や意見交換ができる環境づくりが必要です。一人一人の性格や働き方を尊重した上で、無理のない範囲でコミュニケーションが取れるよう工夫しましょう。
組織の意思決定が遅れるリスクにも
職場の雰囲気が自由になりすぎると、全体の意思決定が遅れるリスクが生じます。これは組織のマネジメントがうまく回っていないことが原因です。
風通しの良い職場では、誰もが意見を出しやすいため、より良い意思決定につながるメリットがあります。ただし、全員の意見を重視しすぎると、意思決定に時間がかかり、業務のスピードが落ちる可能性もあります。
このような場合には、意思決定の過程を明確にするとともに、最終的な判断を誰がするのかを明示する必要があります。
オフィス空間のデザインとレイアウトの工夫
風通しの良い職場を実現するには、オフィスのデザインやレイアウトの工夫も効果的です。
オフィスの移転や改装に伴い、より風通しの良い職場にしたいという方は参考にしましょう。
オープンスペースの活用と適切なゾーニング

職場の風通しを良くするためには、オープンスペースの活用やゾーニングの工夫が欠かせません。
ここでいうオープンスペースとは、通常の執務エリアや会議室とは異なり、個室で仕切られていない広い空間のことです。
そしてゾーニングとは、ワークスペースや共有スペース、情報管理スペースなど、機能別に空間を区切るということ。
オフィス空間を適切にゾーニングすることで、非効率な動線を効率化でき、スムーズに働けるようになります。
コミュニケーションを活性化するレイアウト

コミュニケーションが活発になるレイアウトは、風通しの良い職場づくりに効果的です。
例えば、部署同士を区切るパーティションが心の障壁とならないように高さや素材を工夫する、思い切って執務スペースの間仕切りをなくすといったレイアウトが有効です。
他にも、他部署との交流を活発にするために使う人を固定しないフリーアドレスを採用する、窓際などの空いたスペースにテーブルとイスを並べて雑談スペースを作る、休憩時間に社員が自然に集まれるリフレッシュスペースを設置するといったアイデアもおすすめです。
心理的安全性と快適性を高めるデザイン

職場の心理的安全性や快適さを向上させるために、カフェスペースやミーティングスペースなど、社員が集まりやすくリラックスして会話できるスペースづくりも有効です。
より短いミーティングができるように、立ち話スペースを作るのもおすすめ。必ずしもテーブルなどを設置する必要はなく、腰くらいの高さがある家具があれば十分です。
レイアウト次第では、通路とデスクの間に設置した腰高のキャビネットを置いた場所を立ち話スペースにすることもできます。
風通しの良い職場づくりに向けた10の施策
前項で解説したオフィスのデザインやレイアウト以外にも、風通しの良い職場づくりに有効な様々な施策があります。10の施策をご紹介するので、取り入れられるものがないか検討しましょう。
①フリーアドレスを導入する
風通しの良い職場を作る施策として、フリーアドレスの導入が有効です。
フリーアドレスは、座席を固定せず空いている席で自由に働く仕組みで、座席を日替わりにすることで人間関係の固定化を防げます。
また、部署や役職を超えたコミュニケーションが増え、異なる視点やアイデアを得られるメリットもあります。
毎日席を変える方法や数か月ごとに席替えを行う方法など、業務内容や部署に応じて適切な方式を選びましょう。
②定期的に社内イベントを行う
定期的に社内イベントを実施すると、社員同士の親睦が深められ職場内の風通しがよくなります。
全員が必ず同じ場所に集まる必要はありませんが、同じ趣味を持つ人や同じ価値観を持つ人などが集まれるイベントを行うことで、人間関係の幅が広がります。
業務外で長時間拘束されるのは負担…という場合は、朝会やランチ会など、業務の一環として自然な交流機会を設けるといいでしょう。
他にも、希望者のみが参加できるサークル活動や部活動などを取り入れる方法もおすすめです。

③コミュニケーションツールを導入する
社員同士の情報共有やコミュニケーションを円滑にするため、チャットやアプリなどのツール導入を検討することが有効です。
従業員同士のコミュニケーションが減りがちな場合こそ、コミュニケーションツールの導入が効果的です。
サービスによっては、チャットや1対1のメッセージのやり取りだけでなく、タスク管理やビデオ会議も利用できます。
こうしたツールを活用することで、質の高いコミュニケーションが実現し、職場の風通しもより良くなるでしょう。

④社内アンケートで社員の声を可視化する
風通しの良い職場を目指すには、社内アンケートで社員の声を見える化することも大切です。
アンケートによって、理想と現実のギャップが分かり、社員が日常で感じる不満や悩みを拾い上げることができます。
その結果、改善すべきポイントが明確になり、より良い職場づくりにつながります。
社員が日ごろ感じているコミュニケーション上の不満や問題点を記入してもらうことで、何をどのように改善していけばいいか分かります。より率直な意見を得るために、匿名でアンケートを取る方法もおすすめです。
アンケートを有意義なものにするには、始める前に「なぜ行うのか」「結果をどう活かすのか」を社員へ共有しておくと安心です。

⑤1on1・メンター制度による対話の習慣化を図る
対話の習慣化を図るために、1on1ミーティングやメンター制度の導入を検討しましょう。
1on1ミーティングとは、上司と部下が一対一で定期的に行う面談で、仕事の進捗確認や悩みの共有を目的としています。業務中では言いにくい悩みや課題を自由に話せる機会となるため、風通しの良い職場にするのに役立ちます。
同様に先輩社員が後輩社員に対して、仕事の進め方やキャリアに関する相談に乗るメンター制度も、風通しの良い職場にするのに有効です。
会社によっては経営陣がメンターとなる場合もあり、より広く社員の声を拾い上げられる機会になります。
⑥経営層が率先して対話に参加する姿勢を見せる
より風通しの良い職場を実現するには、経営層が自ら積極的に対話の場に加わる姿勢が欠かせません。
経営層と社員との間の距離が縮まることで、組織全体に一体感が生まれます。
なかには、経営層と従業員が気軽にコミュニケーションを取れるよう、社長室を廃止した企業もあります。
そこまでしなくても、役員室のドアを常時開けておくという方法もおすすめ。いわゆる「オープンドアポリシー」という理念に基づくものです。
オープンドアポリシーは、職場の風通しを良くするだけでなく、信頼関係を強化し組織の透明性を高めるためにも役立ちます。
⑦社員同士が自発的に交流できる文化づくり
社員同士が自然に関わり合える文化を育てることも、風通しの良い職場づくりには欠かせません。
もちろん、勤務中に雑談ばかりしていては問題ですが、業務の話だけに終始する環境では「風通しが良い」とは言い切れません。
仕事とプライベートの切り替えを意識しつつ、気軽に雑談や交流ができる雰囲気を整えていきましょう。
オンとオフの使い分けをしながら、社員同士がちょっとした雑談や交流をしやすい環境を作っていきましょう。
そのためにはリラックスできるスペースの設置や部署間の交流ができるイベント、上司からの積極的な声掛けなどが効果的です。

⑧雑談できる場づくりや音楽環境の工夫をする
具体的な雑談できる場所として、食事や休憩に利用できるカフェスペースの設置がおすすめです。仕事が煮詰まったときの気分転換の場として利用できるだけでなく、社員同士のコミュニケーションを活性化するにも役立ちます。
業務の邪魔にならないようなBGMを流したり、グリーンを取り入れたインテリアにするアイデアもリラックスして過ごすのに役立ちます。
職場の雰囲気を和らげるためにも、カフェスペースの設置を検討してみてはいかがでしょうか。
⑨キャリア支援や制度導入の取り組みを行う
風通しの良い職場づくりには、従業員のキャリア形成をサポートする制度を導入することも有効です。
スキルや知識を学ぶ機会を通じて、業務への活用だけでなく、自身の強みや得意分野を発見することにもつながります。
さらにジョブローテーションや社内留学によって様々な業務経験ができると、部署や部門の垣根を超えたコミュニケーションの幅が広がるはずです。
⑩健康経営やエンゲージメント強化を図る
組織全体で健康経営やエンゲージメント強化に取り組むことは、風通しの良い職場づくりにつながります。
風通しを改善すると多くのメリットがある一方、行き過ぎると馴れ合いや無駄なコミュニケーションを増やすなど、健全な組織運営を妨げる可能性もあります。
そこで役立つのが、定期的なサーベイ(従業員意識調査)です。サーベイによって現状を客観的に把握すれば、良い風通しを保ちながら、必要な改善点を見つけられます。特に組織の成長に欠かせない「社員エンゲージメント」を高めるためにも、サーベイを上手に活用しましょう。
自社に合った取り組みを見つけるには
最後に、自社に合った取り組みを見つけるためのポイントを紹介していきます。
業種や規模に応じた最適解を探る
業種や会社の希望に応じた最適解を見つけられると、風通しの良い職場にするための取り組みが成功するでしょう。
一人ひとりの個性を大切にし、働きやすい環境を実現するには、組織の特長に応じた工夫で風通しの良い職場を築くことが重要です。
例えば製造業では、安全操業に関する情報共有のための定期的な報告会等でのコミュニケーションや、チームワークがポイントに。
デザイン系やクリエイティブな業種では、社内コンテストや社内SNSの活用を通した自由な意見交換を行えるような環境づくりが求められます。
部署ごとの温度差に配慮する
風通しの良い環境をつくるには、部署ごとに異なるスタンスや雰囲気に配慮することが欠かせません。
どのような部署であっても社員間のコミュニケーションは欠かせませんが、組織内のコミュニケーションにおいては温度感を合わせることも重要に。
経営層のコミュニケーション不足は社員の意欲や組織への関与度に影響しやすく、率先して対話の機会を持つことが重要です。
そして人事・総務部門は、社内コミュニケーションに関する制度や施策づくりを企画・実行する部署として、社員の意見を聞きながら温度差を解消するようなアイデアが求められます。
風通しの「バランス感覚」を意識する
上下関係が緩やかになる風通しの良い職場では、人間関係にメリハリがなくなる恐れがあります。
そのため、バランスを意識したやり取りを心がけることが大切です。
あくまでも仕事(ビジネス)における人間関係だということを忘れずに、親しさに偏りすぎず、適度な距離感を保ったコミュニケーションを意識しましょう。
オフィスのご相談はリリカラまで
上下関係がフラットで、誰もが意見を言いやすい職場を「風通しの良い職場」と呼びます。
このような職場には、生産性向上やトラブル時の素早い対応といった利点がある一方で、人によってはストレスを感じたり組織の意思決定が遅れたりするリスクも。
風通しの良い職場を実現するには、オフィス空間や制度面での工夫が欠かせません。
具体的には、フリーアドレスやオープンスペースの活用、コミュニケーションツールの導入、社員が自発的に関わり合える文化づくりなどが挙げられます。
リリカラでは「はたらくをもっとゆたかに」をコンセプトに、ワークスペースを通じて企業の課題解決に向けたサービスを提供しています。最適な働き方の実現に向けたトップインタビューや部門ヒアリング、各種分析調査や空間構築まで、上流部分からサポートいたします。 もちろん、スペースに限りがある場合でも、風通しの良い職場をつくるためのアイデアをご提案可能です。
オフィスのお困りごとは是非お気軽にご相談ください。

社内での交流を促す具体的なコミュニケーション施策を事例を交えてご紹介。空間づくりだけでなくソフト面の施策が知りたい方はぜひご参考ください。